市政方針説明
令和6年第1回市議会定例会において市長が説明した「市政方針説明」について、全文を掲載します。
令和6年第1回市議会定例会市政方針説明
令和6年第1回市議会定例会市政方針説明(令和6年2月26日)(PDF:227KB)
目次
クリックすると直接目的の項目へ進みます
1.安心できるまちづくり
2.ものづくりと世界に貢献する港づくり
3.潤いある文化・観光・スポーツ振興
4.将来を見据えた都市整備と行財政改革
本文
1.はじめに
令和6年第1回定例会の開会に当たり、市政運営に対する私の所信と主な取り組みを申し上げます。
はじめに、本年1月1日に発生した能登半島地震により、亡くなられた多くの方々やご遺族に対し、哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ、甚大な被害を受けられた地域の一日も早い復興を願います。
また、このたびの地震による被災状況を踏まえ、自助・共助・公助による防災対策を基本としながら、市民の暮らしを守ることが私の使命という思いを一層強くするとともに、これからも安全・安心なまちづくりに全力で取り組むことを決意したところであります。
本市では今、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、港まつりをはじめ多くの地域イベントが通常開催されており、また、室蘭・青森間のフェリー就航や大型クルーズ船入港により、まちなかではインバウンドを含む観光客の姿も見られるようになるなど、賑わいが戻りつつあります。
地域経済に目を向けると、燃料や資材価格などの高騰による影響のほか、働き手不足の問題はあらゆる分野で深刻となっておりますが、アフターコロナへの移行は少しずつ本格化しており、全国チェーンを含む様々な店舗が新たに開店するなど、明るい兆しも見え始めております。
コロナ禍の長期化が人々の生活様式や働き方に大きな変化をもたらしましたが、直面する課題に真摯に向き合い、市民が安心して笑顔で暮らせる「住み続けたいまち室蘭」の実現に向けて、全力を尽くす覚悟であります。
2.市政運営の基本姿勢
はじめに、市政運営の基本的な考え方を申し上げます。
最重要課題である人口減少対策では、子育て世帯の負担軽減を柱に、こどもを生み育てやすい環境の充実を図るほか、働き手不足への対応では、企業と連携したUIJターン就職の推進に加え、外国人労働者の活用促進など、広い視野で企業活動を支援し、地元人材の定着や地域経済の活性化に向けた施策展開を図ります。
また、能登半島地震では、人的被害や建物被害に加え、道路や上下水道など社会基盤にも甚大な被害が及んだことを踏まえ、避難行動や災害発生後の対応など、防災対策を強化し、災害に強いまちづくりを進めます。
地域医療については、医師・看護師不足等、医療を取り巻く環境が厳しさを増す中、3病院の連携・再編は必要不可欠であり、第2次中間取りまとめの具現化に向けて、ワーキンググループなどを通じ、各病院や医師会と協議を進め、将来に渡って安心できる地域医療の提供体制構築に取り組みます。
一定程度人口減少が続く中にあっても、安心して暮らせるまちの実現に向けて、将来を見据えた行財政基盤の確立を基本としながら、市民に約束した政策を一つひとつしっかりと形にしていきます。
3.住み続けたいまち室蘭を目指して
次に「住み続けたいまち室蘭」の実現に向けた4つの確かな柱に基づく主な施策を申し上げます。
なお、教育行政に係る基本的な考え方や施策については、教育長より、教育行政方針として申し上げます。
1.安心できるまちづくり
はじめに「安心できるまちづくり」であります。
子育て支援では、昨年から開始した第3子以降の学校給食費やスクール児童館利用料の無償化に加え、0、1、2歳児の保育料の一律引き下げや市独自の多子世帯の負担軽減、医療費助成の18歳までの拡充などに取り組むほか、スクール児童館の開設時間拡大や奨学金返還支援による保育士等の確保など、子育てしやすい環境の充実を図ります。
また、新たにこども家庭センターを設置し、産前・産後サポートや産後ケアを実施するなど、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制を構築します。
さらに、子ども発達支援センターの民営化にあわせ、新たに看護師を配置するなど受入体制の拡充を図り、こどもの療育に対する多様なニーズに対応します。
また、障がい者支援の取り組みでは、38年振りに本市で開催される全道ろうあ者大会を機に、さらなる手話の普及や理解促進を図ります。
キャリア教育では、小中学生向けのふるさと学習による企業見学や地元企業による職業講話など、企業や教育機関と連携した取り組みを進め、人材育成や若者の地元定着につなげます。
災害に強いまちづくりでは、津波警報サイレンとSNSの連携による情報発信の強化や避難場所の拡充に加え、線路横断避難に向けた鉄道事業者との協議など、津波発生時の円滑な避難対策に取り組みます。
また、災害対応ドローンの導入により、被災時の状況確認機能を強化するほか、発電機や暖房器具など厳寒期の災害に対応した備蓄品の拡充とともに、道路が寸断するなど社会基盤の被災を想定した分散備蓄の見直しや水道管のバックアップ機能の強化など、総合的な防災対策を進めます。
さらに、町内会・自治会などによる自主防災組織の広域化を推進するため、資機材購入支援を拡充し、災害時の共助体制を強化します。
高砂町の水質基準値超過への対応では、対象世帯の健康調査などを継続し市民の不安解消を図ります。
2.ものづくりと世界に貢献する港づくり
次に「ものづくりと世界に貢献する港づくり」であります。
洋上風力発電の拠点化に向けては、鉄鋼業を中心とする市内関連産業の集積を活かし、SEP船の寄港誘致等に引き続き取り組むとともに、祝津埠頭における浮体式洋上風力発電の技術開発や、崎守埠頭における部材の組立て・保管等の土地利用の促進についても、チャンスを逃さぬよう、関連企業の取り組みを後押しします。
クルーズ船やフェリーを含めた港湾活用では、港湾振興団体や経済団体と連携して、引き続き船社や企業等へのポートセールスに取り組み、関係する機関や団体の協力を得て、洞爺湖や登別、ウポポイなどの周辺観光とタイアップし、満足度の向上を図っていくとともに、ハード面においては国と連携し、祝津絵鞆地区の岸壁改良や緑地整備を進めるなど、港を通じた地域活性化につなげていきます。
脱炭素社会の構築に向けては、セミナーの開催や専門家の診断をとおして、事業者の省エネ化を支援するほか、企業等との連携による水素サプライチェーン構築に向けた実証事業や、新廃棄物中間処理施設で生成した電力の地産地消など、ゼロカーボンシティの実現に取り組みます。
成長産業への参入支援では、半導体関連産業に関するセミナーを開催し、地元企業の理解促進を図ることで、新たなビジネス機会の創出につなげます。
働き手の確保では、合同企業説明会や外国人採用セミナーを開催するほか、公共交通分野では事業者のイメージアップや国と連携した二種免許取得の支援を行うとともに、介護分野では、事業所の人材紹介企業等を通じた雇用や職員の知識・技能習得への支援など、幅広い分野に対応した展開を図ることで、働き手不足の解消に加え、生活に必要なサービスの維持に取り組みます。
PCB廃棄物処理事業では、昨年末、国より西日本エリアでの受け入れ終了後に新たに発見される高濃度PCB廃棄物の受け入れ要請があったところですが、市民や議会の皆様のご意見も伺いながら適切に判断します。
水産振興では、国・道と連携した漁港整備を着実に進めるほか、関係団体と連携し昆布養殖を主体とする藻場造成の実証事業を支援するなど、つくり育てる持続可能な漁業の確立を後押しします。
3.潤いある文化・観光・スポーツ振興
次に「潤いある文化・観光・スポーツ振興」であります。
文化振興では、市民会館において、カメラシステムなど、老朽化した設備の改修を実施するほか、関係団体のご意見を伺いながら、施設の機能向上に向けた計画的な整備を検討します。
また、南部陣屋史跡では、試掘調査や改修手法の検討を行うなど、市民に親しまれる場所としての適切な維持保全に取り組みます。
室蘭岳山麓総合公園では、四季を通じた利用促進に向けて、キャンプ場に加え、冬季においては、スノーパーク実証事業を実施し、こどもたちが雪と触れあう機会の創出に取り組みます。
水族館では、今後のリニューアルに向けて情報収集を行いながら、基本構想の策定を進め、こどもたちがわくわくする施設の実現につなげます。
観光振興では、民間事業者と連携して地球岬駐車場の利用実態調査を行い、さらなる魅力向上に向けた検討を進めるとともに、地域活性化に熱意のある人材を地域おこし協力隊として募り、情報発信の強化など、交流人口の拡大に取り組みます。
スポーツ振興では、陸上競技場や4月から供用を開始する入江運動公園テニスコートなどの利用促進に向け、大会誘致等に取り組み、市民のスポーツに親しむ機会の創出や、地域の活性化につなげます。
4.将来を見据えた都市整備と行財政改革
次に「将来を見据えた都市整備と行財政改革」であります。
新年度の一般会計予算は、国や道の交付金を積極的に活用したことや、事務事業見直しの徹底などにより、収支均衡を図ったところです。
今後も、市税収入の減少のほか燃料や物価高騰に伴う経常経費の増加など、厳しい財政運営が予想されますが、安定した行政サービスを提供していけるよう、公共施設の適正化や事務事業の見直しなど、不断の努力で行財政改革を進めるとともに、ふるさと納税の積極的なPRやネーミングライツの推進など、歳入確保に努めます。
中島・中央地区の再生に向けては、モルエ中島周辺の交通混雑の緩和に向けた道路拡幅事業に着手するほか、中央地区では、まちづくり会社等と連携しながら、空き地・空き家を活用したまちなか居住の検討を進め、地域の定住人口確保につなげます。
本庁舎や支所の整備に向けては、将来の移転を見据え、事務の効率化に向けた各種システムの導入など、DXを推進しながら、引き続き適正な規模や機能などを検討します。
行政改革では、窓口開庁時間の短縮にあわせて各種証明書のコンビニ交付手数料を減額し、利便性向上と窓口の混雑緩和を図るとともに、本庁舎案内サインの見直しや技術職員育成プログラムの導入など、職員の創意工夫や業務改善提案を、速やかに実施することで、より一層の市民サービス向上と事務の効率化を進めます。
4.むすび
以上、令和6年度における市政運営の基本姿勢と主な取り組みについて申し上げました。
昨年、4年振りに通常開催となった港まつりは、室蘭ねりこみが復活し、大いに盛り上がりました。私も担ぎ手として参加しましたが、威勢の良い掛け声と、それを支える沿道の力水や声援は、元気の結晶であり、途絶えさせてはならない大切な室蘭の文化であることを改めて感じました。
このような活気あふれる姿を目の当たりにしたときに、市民の熱いエネルギーを原動力にして、さらなるまちづくりに取り組んでいかなければならないと思いを強くしたところです。
私が目指す「住み続けたいまち」の実現に向けては、市民や事業者と思いを共有し、市民が暮らしやすいと共感できるまちを、ともに作り上げていくことが最も重要であると考えています。
そして、これからのまちづくりでは、前例の無い課題も想定されますが、そのようなときこそ、市民や職員、さらには室蘭に所縁のある市外の応援者の方とも手をとりあって、負けてたまるかという姿勢で、私の持てる力の限りを尽くして挑戦していく決意であります。
むすびに、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
お問い合わせ
企画財政部企画課企画係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2181
ファクス:0143-24-7601
Eメール:kikaku@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

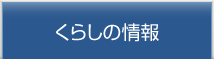
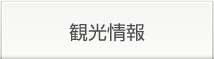
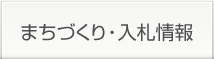
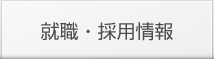
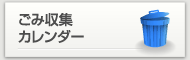
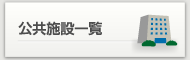
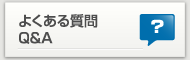
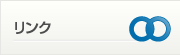
![携帯サイトはこちらから [https://www.city.muroran.lg.jp/im/index.html]](/shared/image/i_left/qr_ja.gif)
